AAR Japan特別インタビュー 東日本大震災は何を残したのか 阪本 真由美さん(兵庫県立大学大学院教授)
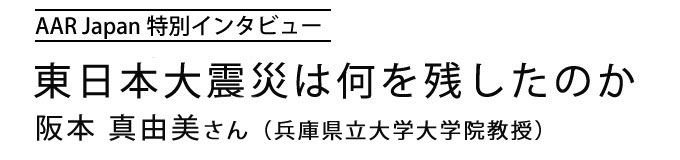

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、東北3県を中心に死者・行方不明者2万2,000人余り(震災関連死含む)に上る未曽有の被害をもたらした。あの日から間もなく10年。地震・津波に原発事故が追い打ちをかけた被災地では、復興に向けた懸命の努力が続いてきた。被災地の障がい者支援を通じてAAR Japanと協働していただいた兵庫県立大学大学院・減災復興政策研究科の阪本真由美教授に10年間を振り返ってもらった。
(聞き手:AAR Japan 中坪央暁/2021年1月13日にインタビュー)
復興の現状に地域格差
――東日本大震災の発生直後から被災地の行政支援、復興・防災政策の提言に携わってこられた立場で、この10年間をどう受け止めていますか。
阪本氏 もう10年経つのか、早いなというのが実感ですね。被災地復興の現状を見て、強く感じるのは、地域差が大きいということです。地震と津波に襲われた岩手・宮城両県と、それに原発事故が加わった福島県では大きな差があります。岩手・宮城の中でも避難していた住民が戻った地域、人口流出で過疎化が進み、ますます厳しくなった地域がありますし、福島では今も故郷に帰れない方々がたくさんいます。広域避難や風評被害も重なって人と人の関係性が失われている点も、通常の被災地とは異なると思います。私は海外の紛争地を研究していた時期があるのですが、紛争で敵対したり壊れたりした人間関係を再構築する和解・対話、人と人との接し方、地域の関係づくりなど、日本の被災地と言うよりも海外の紛争地に近いような事象さえ見られて、非常に不思議な気がしたものです。
また、阪神・淡路大震災(1995年)では、がれきを撤去して被災地をそのまま復興すれば良かった訳ですが、津波で壊滅した東北沿岸部の場合は、まず町全体をかさ上げしたうえで復興に着手したり、住宅地をそっくり高台に移転したりしなければならず、それだけ時間がかかっています。そういう点でも、東日本大震災の特異性、他との被災地との顕著な違いが見られます。
ハード面の整備では、何かと議論もあった津波対策の巨大防潮堤の建設が進みましたが、そうした防災設備が特定のハザード(危険性)に対する機能しか持たない危うさも明らかになっています。例えば海側からの津波は防げても、大雨が降った時に陸側からの排水機能が弱くなり、かえって水害を生んでしまう事態が岩手県内で実際に起きています。防災・減災におけるハードの難しさを改めて感じます。

東日本大震災の被災地支援に入り、村井嘉浩・宮城県知事(右)と面談する阪本さん(左から2人目)=同県庁で2011年3月
宮城県庁で緊急支援サポート
――東日本大震災の直後、宮城県庁で緊急支援の後方業務に取り組まれたと伺っていますが、具体的にどんな立場でどういう仕事をされたのでしょうか。
阪本氏 私は2011年当時、阪神・淡路大震災をきっかけに兵庫県が主体となって設立した「人と未来防災センター」(神戸市)の研究員でした。同センターは大震災当時の兵庫県知事だった故・貝原俊民さんが「行政トップとして孤独だった」、つまり「緊急時に周囲に参謀役がおらず、自分の責任ですべて判断しなければならなかった」と述懐されたのを受けて、大震災の経験を将来に生かし、災害発生時に行政のアドバイザーになる人材を育成することを目的に創設された機関です。他県の被災地のサポートも主要なミッションで、私たちは震災3日後の3月14日に宮城県庁に派遣され、6月末まで後方支援に就きました。
ひと言で言えば、政府の緊急災害対策本部(内閣府)と現地対策本部(宮城県)をつなぐ情報収集、および問題解決の提言が任務でした。当初は津波で壊滅した沿岸部の情報が全く入らず、どこで何を支援すれば良いのか必死で情報を集めました。災害対策基本法では対策本部設置までは定められていたのですが、現場レベルで具体的に何をするのかノウハウを誰も持っておらず、私たち後方支援チームは避難所にどうやって温かい食事を届けるか、義援金の配付の仕方、被災者のワンストップ相談窓口の開設、果ては行方不明者の捜索をいつ打ち切るかといったことまで、ありとあらゆる問題の対応に追われました。緊急期の支援がいったん終了した後、災害対応の検証業務で9月に再度、宮城に戻って問題点を洗い出す作業をしました。
災害時の障がい者支援
――AARは発生直後から緊急支援物資の配付や炊き出しを行い、その後は支援が届きにくい障がい福祉施設を中心に復旧支援を続けました。岩手・宮城の沿岸部では、知的あるいは身体障がいのある方々の死亡率が全体の2倍に上ったというデータもありますが、被災地の障がい者支援はどんな状況だったのでしょうか。
阪本氏 東日本大震災では、まさに災害時の障がい者支援の重要性が浮き彫りになりました。津波で逃げ遅れた犠牲者の中には、肢体不自由な方が多く、それを助けようとした民生委員も多数亡くなっています。避難所でも障がい者や重病者に対する特別な配慮はなく、障がいのあるお年寄りがオムツを交換しようにも仕切りさえなかったり、末期がんの家族を病院に搬送する手段がなく道端で亡くなったり、福祉避難所に指定された施設のケアマネージャー自身が被災していたり、切ないことばかりだったのですが、それに対して何もできないもどかしさを痛感しました。障がい者支援をどのように行うのか、市民ネットワーク「障がい分野NGO連絡会」(JANNET)やAARの皆さんと集まり、福祉施設への支援物資提供について協議したのがお付き合いの始まりです。

岩手県山田町の避難所で過ごす被災住民=2011年3月、川畑嘉文撮影
災害対策と障がい者支援をリンクする問題意識はこの10年間、行政サイドや政策レベルでも共有され、災害対策基本法で障がい者・高齢者を「災害時要介護者」と定めて、いざという時に助けを必要とする「避難行動要支援者」リストも各自治体で作成されています。また、福祉避難所の公開や避難所内の福祉スペースの設置に関する法律改正も行われる見通しです。障がい者支援についての意識はある程度高まったとはいえ、これですべて解決する訳ではありません。平時は障がいのある方々を思いやることができても、誰もが極限状態に置かれる災害時は「みんな平等に」という公平性が優先され、障がい者だけに特別に配慮する余裕がなくなるのが現実です。そうなると、支援物資の受け取りひとつでも障がい者が取り残される恐れが生まれるので、制度構築に加えて、障がい者に特化したNGOや支援団体の役割が引き続き重要になると考えます。
紛争研究から防災分野へ
――阪本さん自身が防災分野の研究者になった経緯は。
阪本氏 少しお話しした通り、もともと海外の紛争問題に関心があって、神戸大学大学院で中南米の紛争と民主化を研究していました。阪神・淡路大震災が起きる直前の1994年12月、1992年に内戦が終結したエルサルバドルの日本大使館に専門調査員として赴任したので、実は震災を経験していないんですね。しかし、何が起きていたのか知りたいという気持ちが逆に強くなり、自分でいろいろ調べました。国際協力機構(JICA)に入職して東京本部に配属されましたが、折から1999年にトルコ、コロンビア、台湾で大地震が相次ぎ、私も災害支援に関わることになりました。日本の被災経験と防災のノウハウを世界に発信する機運が高まっていた2002年、JICA神戸(現JICA関西)に異動になり、翌年JICAの中で部局横断的に立ち上げられた「防災タスクフォース」に加わって、開発途上国の関係者の防災研修を神戸に集約するなど、防災分野の実務に取り組みました。その後トルコ事務所で2年間勤務するうちに、防災を自分の専門にしたいと考え、JICAを退職して京都大学大学院の博士課程に進みました。
博士論文の研究テーマは、2004年のインド洋大津波で壊滅的被害を受けたインドネシア・スマトラ島のアチェ州、2006年に起きた同国のジャワ島中部地震の被災者の生活再建です。住民の8割が津波で亡くなったアチェ州のウレレ地区では、当初は国連機関が建てた簡素な復興住宅が並んで殺風景でしたが、徐々に樹木が増えて植生が整い、コミュニティが再生されていく様子が見て取れました。東北沿岸部の造成地も、時間が経てば少しずつ表情を取り戻していくのかも知れません。

インドネシア・アチェ州の大津波被災地の調査に訪れた阪本さんと子どもたち=2007年8月
博士課程を修了して「人と未来防災センター」に入り、国内の災害対策の仕組みを学んでいた一年後、折から東日本大震災が発生して、研究成果を被災地で実地に生かすことになった訳です。現在は兵庫県立大学大学院に2017年に開設された減災復興政策研究科で、防災教育、防災危機管理、国際協力を担当する傍ら、内閣府や国土交通省、自治体などの防災関連の委員会メンバーを務めています。
「創造的復興」を世界に発信
――この10年間で実現できたこと、そして残された課題は何だと思いますか。
阪本氏 阪神・淡路や東日本の震災経験を踏まえて、「創造的復興」の概念を日本から世界に発信できたことは、ひとつの大きな成果だと思います。被災地を単に震災前の状態に戻すのではなく、次の災害に備えてより強靭な地域社会を構築するという発想は、貝原元知事が最初に提唱した考え方ですが、ビル・クリントン元米国大統領が〝Build Back Better〟という言葉にしたことで世界に広まりました。国際的な防災戦略について話し合う「国連防災世界会議」は過去3回、横浜(1994年)、神戸(2005年)、仙台(2015年)といずれも日本で開催され、日本が提案した「世界津波の日」(11月5日)も国連総会で制定が決まりました。
その半面、島国であるためか日本の防災戦略は自己完結型で、近隣諸国との協力関係づくりが弱い気がします。東日本大震災の復興では海外からの支援が大きな役割を果たしましたし、将来予想される南海トラフ地震や首都直下地震が起きたとしたら、近隣国からの緊急支援なしには乗り越えられないでしょう。日本は開発途上国に対するJICAの防災・減災支援、国際緊急援助隊の派遣など国際貢献をしていますが、逆に支援を受け入れるシステムを整備する必要があると考えています。
また、災害に備えるプロパーの政府機関がないのも問題です。災害が発生する度に、首相を本部長とする緊急災害対策本部が内閣府に臨時に設置され、内閣府の調整によって関連省庁や地方自治体が部局横断的に対応していますが、「数十年に一度」と言われる台風・水害などが相次ぐ昨今、充分な専門性を有する防災スタッフを配置した「防災省」のような常設機関が必要ではないでしょうか。そこで過去の災害対応や防災のノウハウを集約するとともに、都道府県や市町村レベルの職員研修を実施することを提案します。それは私自身が東日本大震災の行政の現場で得た教訓でもあります。
行政・企業・NGOの連携推進
――防災・減災や被災地支援の現場で、AARのようなNGOが担うべき役割、行政や企業など他のプレーヤーとの連携について、どうお考えですか。
阪本氏 東日本大震災の被災地でNGOが果たした役割は非常に大きかったと思います。大規模災害時には、地方行政や自衛隊、警察・消防、社会福祉協議会、民間企業、NGOなど多くの関係者が、それぞれ連携して役割を担うことが求められます。2016年に設立された(特活)全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)は、より効果的な被災者支援を実現できるように、政府・自治体や企業、支援団体などの立場を超えた連携の促進を図っています。官民連携による「情報共有の会議」の設置が定着しつつありますが、もう一段レベルを上げて、意思決定の場にしていければと考えます。併せて、避難所の運営、障がい者支援、子どものケア、廃棄物処理などセクターごとの専門性を高める必要も感じています。

AAR Japanによる宮城県石巻市での巡回診療活動=2011年5月、川畑嘉文撮影
ひとつ指摘しておきたいのは、日本では防災を行政に依存し過ぎているということです。行政がスリム化され、市町村合併で行政域が広域化したことで、自治体の防災体制は全国的に脆弱になっており、企業やNGOなど民間セクターとの連携なしには災害に対処できません。緊急時に行政にできることは限られているのです。
阪神・淡路や東日本では、AARのように海外の難民や被災地支援の経験を積んだNGOが、そのノウハウを国内の被災地で生かして活動しました。災害に関わるNGOの強化、あるいは災害支援に特化したNGOが増えることを期待します。日本ではNGOがボランティアとひとくくりに混同されがちですが、NGOはボランティアではなく、専門性を生かし、ニーズがある限り現地に留まって活動を続けることを仕事としています。
そうしたNGOの活動を資金面で支えるためには、市民社会の一員としての企業の取り組みが重要だと考えます。例えば日本赤十字社に義援金を贈れば社会的責任を果たせると考える方もおられると思いますが、義援金は県の配分委員会を経て被災者に分配されるものの、一刻を争う緊急支援や地域全体の復興を促進するための資金にはなりません。NGOへ寄付金と義援金は全く違います。また、ジャパン・プラットフォーム(JPF)のように、海外でのNGOによる人道支援活動を公的資金で助成する仕組みはありますが、国内災害に関してはありません。災害対応に特化した官民のファンドを創設し、企業の寄付や公的資金をプールして、災害発生時に緊急出動するNGOに分配・助成するシステムがあれば、非常に有効ではないでしょうか。
東日本大震災の被災地の復興は道半ばですが、この10年間に得られた多くの知見を生かし、日本と世界の防災・減災の取り組みに貢献していかなければならないと改めて感じています。また、災害時に避難情報が発令されても逃げない人が多いことが問題になっていますが、防災は決して他人事ではなく、私たち一人ひとりの責任であるという意識を高める必要もありそうです。
|
ひとこと 阪神・淡路大震災当時、渦中で暮らしていた私は、神戸や西宮の惨状を目の当たりにしながらも、直感的に「数年で復興するだろう」と思った。社会・経済インフラが集積する大都市圏だからである。対して、先頃訪ねた東北の被災地は、津波に飲まれた沿岸部も、原発事故の影響を受けた山間部も、復興とはおよそ程遠い印象を受けた。「10年は節目ではない。震災は今も続いています」という地元の方の言葉が耳に残る。(N) |
|
【報告者】 記事掲載時のプロフィールです
東京事務局 中坪 央暁
全国紙特派員・編集デスクを経て、国際協力機構(JICA)の派遣で南スーダン、ウガンダ北部、フィリピン・ミンダナオ島など紛争復興・平和構築の現場を長期取材。新聞社時代にはアフガニスタン紛争、東ティモール独立、インドネシア・アチェ紛争などをカバーした。2017年11月AAR入職、2019年9月までバングラデシュ・コックスバザール駐在としてロヒンギャ難民支援に従事。著書『ロヒンギャ難民100万人の衝撃』(めこん)、共訳『世界の先住民族~危機にたつ人びと』(明石書店)ほか。栃木県出身

