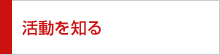夏休みに親子で考えた、「被災地のために私たちができること」
自分だったらどうするだろう? ワークショップで疑似体験

被災地に何が必要か、ワークショップを通じて考えました(右は難民を助ける会の穂積武寛)
8月4日、難民を助ける会事務所で、小中学生対象の夏休み体験教室「東日本大震災 みんなで考えよう 被災地のために私たちができること」を開催しました。小中学生とその保護者約30名にご参加いただき、被災地に支援物資を実際に届けるまでを追体験するワークショップを通して、緊急支援の進め方や難しさを考えました。東日本大震災だけでなくハイチ大地震やパキスタン洪水の被災者支援について学び、国際協力のために自分ができることについても考えました。最後は世界各地のお菓子やお茶を味わいました。暑い中ご参加いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。
ご参加くださった方からの感想を、一部ご紹介します。
- ワークショップがとても面白かった(中1女)
- 被災地の人たちや、物を届ける人の気持ちがよくわかった(小6女)
- 他の参加者と考え、話すことができたのが良かった(中2女)
- 買い物をするのが楽しかったです(小2男)
- 実際の写真とか現場に行ったことのある人の話を聞けるのはとても良い経験だと思います(小6女)
- 相手の立場になって考えることに子どもたちが気づけたことが勉強になりました(保護者)

難民を助ける会の東日本大震災での支援活動を写真で紹介しました

グループに分かれて被災地に支援物資を届けるワークショップ。グループ名は何がいいかな?

さぁ難民を助ける会のスタッフになって、支援物資を買いに行くよ。予算は3万円。どれにするか迷ってしまうね

自分たちが買った支援物資と、選んだ理由をグループリーダーが説明します

お母さんたちには被災者役になってもらい、避難所に何が必要か考えてもらいました

物資を届ける側と、受け取る側。求められているものを届けられたかな?

世界には困っている人たちがたくさんいます。ハイチ大地震のときにはこんな物資を配りました

ワークショップの後は、世界のお茶とお菓子を楽しみました。一番の人気はラオスのバナナチップスでした