知ってもらわないといけないことがある 川畑嘉文さん(フォトジャーナリスト)
2023年6月12日

インタビューに答える川畑嘉文さん
フォトジャーナリストの川畑嘉文さんは、世界各地の紛争地帯、大災害の被災地など訪れ、写真を撮り続けている。AAR Japanの緊急支援チームに加わって活動した経験もあり、この6月に開催する「世界難民の日写真展」にも協力していただいた。どんな悲惨な場面でも、その底に人間のぬくもりが感じられる川畑さんの写真。どうしてそんな写真が撮れるのか聞いた。
(聞き手:AAR東京事務局 太田阿利佐/5月25日にインタビュー)
――これまでにAARとたくさん仕事をして下さっています。
川畑さん 2006年にアフガニスタンの首都カブールで、AARの人道支援活動を撮影したのが最初です。2009年のフィリピン台風被害、翌年のハイチ大地震、2011年の東日本大震災では、記録・広報用の写真撮影だけでなく、緊急支援物資の配付なども手伝わせていただきました。新型コロナウイルス流行前の2019年にはカンボジアで障がいのある子どもたちを、2022年のロシアによるウクライナ侵攻直後にはモルドバで難民の女性や子どもたちを撮影しました。

「居住地に移動する南スーダン難民たち」2016年ウガンダで川畑嘉文撮影
――「世界難民の日写真展『今、地球のどこかで』」(モンベル御徒町店で6月開催)では、川畑さんの作品も多数展示されました。ぜひ見てほしいと思う1枚はありますか。
川畑さん う~ん…それぞれに思い入れがあります。でも、もしあえて選ぶとしたら、2014年に撮影したシリア難民の男の子の1枚でしょうか。

2014年トルコで=川畑嘉文撮影
この男の子の一家はシリア北部の村で暮らしていました。内戦で空爆が激化して隣家が全焼し、「イスラム国(IS)」の支配が及んできたため、すべてを捨ててトルコに避難することを決意しました。なんとか国境ゲート近くまでたどり着いたものの、そこにもIS兵士がいて通過できない。持ってきた食料も底をつき、最後の手段として徒歩で国境地域を越えようとした、その途中で地雷が男の子と兄を吹き飛ばしたのです。
男の子は両脚を切断し、大好きだった兄は死亡しました。男の子は毎日「兄さんはどこにいるの?」と聞くのだそうです。父親は「本当のことはとても言えない。出稼ぎに行ったんだよと答えています。これが一番つらい」と語っていました。私も通訳もドライバーも、その話を聞きながら涙が止まらなかった。思い出すと今でも涙が出そうになります。
彼らはただ、安全を求めただけです。その結果、地雷で命や手足を奪われるとは……救いがないとはこのことだと思いました。この地球には、未だにこんな人々がいる。知ってもらわないといけない。そう思いながらシャッターを切りました。
――「知らせるためにシャッターを切る」。そういう使命感は最初からあったのでしょうか?
川畑さん 僕は、初めからカメラマン志望だったわけではないんです。英語以外の勉強が苦手で、大学進学に悩んで、いっそのこととおもって米国に留学しました。ペンシルバニア州立大学で国際政治を専攻し、卒業後はニューヨークにあった日本人向け情報誌の記者になりました。そこで遭遇したのが、「9・11」(2001年米同時多発テロ)です。あれで人生が変わりましたね。
2機の航空機が突入して崩壊したワールドトレードセンター・ビルの辺りには、それまで何度も取材に行っていたので、とても信じられない思いでした。もちろん取材しましたが、あの時、1枚の写真の力がどれほど大きいのか思い知ったのです。
うまく言えないのですが、あの時以降「文章を書くより写真を撮りたい」と強く思うようになりました。翌年、会社を辞めて、米英軍がタリバン政権を倒したばかりのアフガニスタンに飛びました。米国の侵攻による傷跡を記録したいと考えたからです。まだカメラマンとしての勉強も不十分でしたが、「とにかく世界を見てみたい」「自分が知らないものをのぞいてみたい」という好奇心からでした。

「荒野にテントを貼って暮らすシリア難民」2012年トルコで、川畑嘉文撮影
――その後、川畑さんが訪れたのは旧ユーゴスラビア、カンボジア、パキスタンなど約50カ国・地域に上り、2冊の本『フォトジャーナリストが見た世界』『フォトジャーナリストが撮った世界の現実』(いずれも新評論)を出版されています。危険な地域も多いのに、よく無事でしたね。
川畑さん アフガニスタンは僕の原点のような場所。2002年から何度も訪れていますが、最初の訪問の時に歩き回っていた場所が、実は地雷原だったと後で知って、ぞっとしたことがあります(笑)。運が良かったのでしょう。
確かに僕は危険な国や場所を訪れることが多いのですが、海外のメディアはそうした場所でも積極的に記者やカメラマンに取材させています。むしろ日本のマスメディアが消極的なんです。危険な場所の記事や写真は、主に外国通信社やフリーランスから買っている。報道機関なのにそれでいいの?と思うこともあります。
僕が撮影している報道系・ドキュメンタリー系の写真は、とにかく発表の場が少ないのも日本の特徴です。かつてあったドキュメンタリー系の写真雑誌は、ほとんど姿を消してしまいました。写真展の機会も決して多くない。機材を整えて、危険と隣り合わせの現地に行って……必死にシャッターを押して撮影した写真でも、販売先や展示の機会が限られているので、利益はほとんど出ない。使命感がないと続かない仕事です。
それでも誰かがそこに行かないと、何が起きているかは分からない。誰かが伝えないと、社会は変わらない。写真は社会を知ってもらうためのツールだと思っています。もちろん写真を見た人がどうするかは分からない。忘れてしまうかもしれないし、AARのような人道支援団体に寄付してくれるかもしれないし、全く別の行動をするかもしれない。それは分からないけれど、とにかく自分が目にしたものをまず伝えたい。それは僕だけじゃなくて、カメラマンはみな一緒だと思います。

「大学の寮で避難生活を送るウクライナの家族」2022年モルドバで、川畑嘉文撮影
――写真をきっかけに思いがけないことが起きる場合も?
川畑さん 時々あります。東日本大震災の被災地の撮影は、本当に辛かったです。ひどい現場を目にするだけでも胸が痛むうえ、「写真なんか撮ってんじゃないよ」という被災者の方々の声も度々聞きました。それでも、何がどんなふうに起きたか後から確認するためにもと撮影を続けました。宮城県女川町の避難所で、たまたま撮影した1枚をAARのホームページに掲載してもらったのですが、何年も経ってから「写っているのは私の父です。この写真をいただけませんか」という方が現れた。震災の津波で、アルバムを流され、写真がほとんど残っていないということでした。ああ、写真はこんなふうに人の役に立てるんだ、救われた気がしました。
ジャーナリストは「知らせるために現場に行く」けれども、実際に困っている人に手を差し伸べられるわけではない。何もできないんです。でも、AARと一緒に行動して、実際に支援活動にも携わって、物資をお届けしたりすると、「ありがとう」って声をかけてもらえるじゃないですか。それが僕には心の支えになっている部分もあります。
――今後ともよろしくお願いします。
川畑さん もちろんです。新しい現場だけでなく、以前に撮影した人々が今どうしているか、ぜひ再会して写真を撮ってみたいですね。災害現場でも難民キャンプでも、「こんなひどい状況なのに、こんなに温かく迎え入れてくれるなんて」と感じることがあります。そうして迎えてくれた人々に、僕はまだ恩返しができていない。僕にはおカネも権力もないけれど、僕の写真を見た誰かが何か行動してくれることで、間接的に恩返しをすることはできる。それさえ信じていれば、この仕事を続けていけると思っています。
ひとこと 「僕、気弱なんで」。インタビュー中、川畑さんは何度かそう口にした。気弱な人間が、たくさんの荒々しい現場に踏み込んでいけるわけはない。なのに「本当に気弱では……」と思わせるところがある。不思議な人である。地雷で脚を吹き飛ばされた少年を抱く父親の1枚は、まるでミケランジェロの「ピエタ像」のように私には見えた。悲惨な現実を写して、そこに神々しさがある。(O)
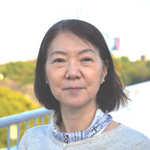
太田 阿利佐Ota Arisa東京事務局
毎日新聞記者を経て、2022年6月からAAR東京事務局で広報業務を担当。



