支えてくれた日本の人々 今は恩返しの時 森スワンさん(元ベトナム難民/AAR常任理事)
2023年9月8日

インタビューに答える森スワンさん
ベトナム難民として約40年前に来日した森スワンさん(53歳)は、上智大学大学院で博士号を取得し、現在は大学でベトナム語を教えています。この6月、AAR Japan[難民を助ける会]常任理事に就任しました。ウクライナをはじめ世界の難民問題への関心が高まる今、「元難民」としてのこれまでの歩みと思いを聞きました。
(聞き手:AAR東京事務局 太田阿利佐/8月29日にインタビュー)
迫害を逃れて12歳で日本へ
――ベトナム戦争は1975年に北ベトナム側の勝利で終結し、この前後からべトナム、ラオス、カンボジアが相次いで社会主義体制に移行しました。これら3カ国から脱出した人々を「インドシナ難民」と呼びます。森さんがベトナムから難民として来日したのは1982年、12歳の時ですね。
森さん 私は兄2人、姉6人の9人きょうだいの一番下です。父は南ベトナム政府の高官で、カトリック教徒でもあったため、私たち家族は迫害の対象になりました。父は3年以上、ジャングルの中で身を潜めるように生活していました。5歳上の兄は、小舟に乗るなどして7回もベトナム脱出を試みました。「ボートピープル」と呼ばれるベトナムからの流出難民は1990年頃までに約150万人に上り、そのうち他国に無事にたどり着いたのはわずか30万人と言われています。まさに命がけの脱出でした。
ボートピープルは世界的な問題となり、1980年代に入って日本でも離散家族の呼び寄せが認められるようになりました。一番上の兄がすでに日本に留学していたので、私たちは合法難民として飛行機で日本に来ました。でも、ベトナムで結婚していた上の姉3人は、同行を許されませんでした。

ベトナムで暮らしていたころの写真 中央の女の子が森さん
姉や兄と夜中の2時まで勉強
――AARが前身である「インドシナ難民を助ける会」として発足したのは1979年11月。当時の日本社会には、難民受け入れの経験がありませんでした。ご苦労されたのではないですか。
森さん 私たちを受け入れ、いろいろと支援していただき、日本の方々には大変感謝しています。でも確かに、日本語をはじめ、多くの困難がありました。両親は高齢でしたので仕事に就くことはできず、一番上の兄が主な働き手でした。それでは一家8人の生活は難しいので、3人の姉は昼間はホテルで働き、夜は日本語学校に通い、夜中の2時頃まで大学進学のために勉強をしていました。すぐ上の兄はもう18歳でしたが、地元の中学の2年生に編入され、13歳になっていた私は小学5年生に編入しました。
――その頃から、森さんもお兄さんも連日夜中の2時まで勉強されていたそうですね。
森さん 当時は児童・生徒への日本語支援の仕組みはなく、授業では「放置」の状態でした。授業は全く分からないし、日本語ができないので友達も作れない。本来の年齢より3年も下の学年に入ったので、周囲の子たちも戸惑っていたのかもしれません。兄も同じ状況でした。本当に孤独でした。この状況から早く抜け出したい、そして高等教育を受けて、社会の役に立つ人材になって、ベトナムを再建したいという思いが強くありました。でも夜中の2時まで勉強したのは、当時は家が狭くて、姉たちが起きていると私も眠れなかったというのもあるんです(笑)。
来日後数カ月の日本語研修の後は、難民への支援は何もない。そんな時代に最初に手を差し伸べてくれたのが「助ける会」でした。まず、奨学金の支給です。当時は条件をつけずに学生全員に奨学金をくれました。私だけでなく兄も姉も支援を受けられました。また衣服や文房具などもいただきました。日本語と学校の勉強を手伝って下さるボランティアの方も紹介してくれました。一対一で面倒を見てくれる人がいたのは、とてもありがたかったです。この方は、私の学校にまで行って、先生と話をしてくれました。一対一のサポートなど、国にはそこまでできません。国ができないことをやる、そこにNGOの意義があると思っています。
そのころは毎年夏合宿があって、富士山とか千葉・銚子とか日本全国あちこちに連れて行ってもらいました。難民の家庭は、どこも生活に精一杯。旅行をする余裕などありません。助ける会の合宿が、難民の子どもたちの夏休みの唯一の楽しみでした。また、普段は言えない日々の寂しさやしんどさも、そこでは口にできました。現会長の長有紀枝さんも、若手職員として参加されていたんですよ。「おねえさん」「おねえさん」と子どもたちから慕われて、大人気でした。難民の子どもたちの話を聞きながら、黙って涙を流されていた姿を今でも忘れません。難民の子どもたちは、自分の話を親身に聞いてくれる人がいる、それだけで慰めになった、ということなんでしょうね。夏合宿は、ああ、こんなに良い人たちが日本にはたくさんいて、自分たちを応援してくれている、そう実感でき、励まされる場でした。

富士山頂での合宿 みんなと山頂で記念撮影
視野が広がった米国留学
――猛勉強の末、お姉さまたちは女子大へ、お兄さまは大学医学部に、森さんはICU高校(国際基督教大学高校)に進学しました。
森さん 兄も私も助ける会の合宿で吹浦忠正さん(現AAR特別顧問)に相談にのっていただき、進学できたのです。でもICU高校は、豊かな家庭で育ち、英語ができて当たり前という生徒が多くて、やはり私は孤独でした。「英語ができないと今の環境を楽しむことはできない」と考え、米国留学を目指しました。幸い奨学金を得ることができて、1年間、素晴らしいホストファミリーに恵まれて留学生活を送ることができました。米国は民主主義の国、移民を受け入れる懐の深い国でした。私の視野も広がり、学校生活が楽しめるようになりました。
助けてくれる人いるかがキー
――森さんは2004年、「難民がジャパニーズ・ドリームを持てる国に」との提言を発表しています。難民個人の努力は必要だが、国としても外国出身者を支援し、採用・登用・活用を推進することで活力を生み、よりよい社会を作ろうとの提案でした。それから約20年、今の日本をどうご覧になりますか。
森さん 小中学校での日本語学習支援の必要性が認識されるなど、進んだ面もあります。一方で難民の就職問題など、ほとんど進んでいない面もあるようです。思春期に来日した難民の子どもたちへの支援もそうです。日本語がまだ不自由だから高校や大学への進学が難しい。経済的な問題があり、16~17歳から働くことを選ばざるを得ない子どもたちがいます。でも日本語力が十分でないので、職場では怒られてばかりで、いつまでも安い賃金しかもらえない。つらくて仕事を辞め、道を踏み外すようなことになったら、日本社会にもマイナスです。
とはいえ、国の政策はなかなか変わりません。結局は本人が頑張るしかないのです。でもそこで、NGOとかボランティアとか、助けてくれる人がいるかいないか。それが全てのキーになる。
私たちきょうだいはみな高等教育を受けることができましたが、それは一番最初、一番苦しかった時にAARを知り、AARを通して日本の皆さんの支援を受けることができたからです。もう40年以上日本に住み、今は日本が私の国。日本社会にそのご恩を返したいと思っています。

インタビューに答える森スワンさん
ニーズに素早く対応する
――AARの日本国内での難民支援は1992年に姉妹団体「さぽうと21」に引き継がれました。他方で昨年来のウクライナ避難民の来日を受けて、AARも再び日本国内での難民支援に取り組んでいます。これからのAARに求めるものは何ですか。
森さん 「困っている人のニーズに、ダイレクトにスピード感を持って対応する」。40年以上前の会の創設者・相馬雪香先生(故人)の精神は、今もAARの緊急支援活動の素早い開始などに引き継がれていると思います。これを維持することです。AARは大きな組織になり、いまや世界中で困っている人を救援しています。素晴らしいことです。しっかり続けてもらいたい。
AARがこうした活動ができるのは、すべて支援者の方々の寄付のおかげです。ウクライナ危機もそうですが、世界には悲劇があふれています。自分は小さい、自分が頑張っても何もよくならないと悲観的になりがちです。でも、あなたの善意や寄付をAARに託していただくと、1円でも100円でも困っている人たちに届きます。大きいことはすべて小さいことから始まる。希望を持っていきましょう。
ひとつの考え方として、私は支援者の皆様にそうお伝えしたいです。では、自分の大切なお金を託す対象として、どうしたらAARを信頼していただけるでしょうか。私は学生の時からAARの支援を受け、社会に出た後は理事として、合計40年以上AARを見てきました。私は、AARとさぽうと21の活動の「生き証人」です。どうか私の話を参考にしていただきたい。そして私とご一緒にこれからもAARに関わり、ご自身の目で活動の在り方を確かめていただきたいと思います。
善意のある日本人はたくさんいるんです。しかし、自分たちの善意をどうしたらいいのか、どこに注いだらいいのかよく分からない。その善意を受け取り、かつての私のような難民に届けてつなげる、それがAARの役目だと思っています。助けたいと思う人と困っている人が出会う場をつくるということです。
つらいことほど言えない
――これまで、森さんがご自身の歩みを語られることは、ほとんどありませんでしたね。
森さん 社会の片隅で、ひっそりと生きていたいと願ってきました。難民としての昔のつらかったことに触れるのはやはり難しいです。当事者はつらいことほど言えない。でもAARの常任理事に就任し、自分がきちんと語ることで誰かのためになるなら、頑張るしかない、と今は思っています。ご恩返しですね。
ひとこと 森さんのお話を聞きながら、10代の頃に読んだ漢詩の一節をふと思い出しました。「君看ずや双眼の色 語らざれば憂いなきに似たり」。語らなければ何の憂いもないかに見えるけれど、あの二つの瞳の奥にたたえられた、深い深い悲しみを見てごらんなさい――という詩。森さんは、まさにこの詩のように深く、そしてやさしい眼をしていました。今、つらい思いをしている多くの難民の人々の代わりに森さんは語ってくれたのだ、と気づいた時、胸が熱くなりました。(O)
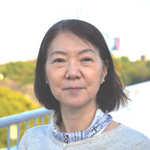
太田 阿利佐Ota Arisa東京事務局
毎日新聞記者を経て、2022年6月からAAR東京事務局で広報業務を担当。



