関わり続けることが心の支えになる サヘル・ローズさん(俳優/タレント)
2022年12月9日

インタビューに答えるサヘル・ローズさん
俳優やタレントとして活躍するサヘル・ローズさん(37歳)は、世界各地の難民や子どもたちとつながり、個人的に支援を続けている。7歳まで祖国イランの孤児院で過ごし、8歳で養母フローラさんとともに来日。さまざまな壁にぶつかりながらも「寄り添ってくれた人がいたから今がある」と語るサヘルさんに、人を支援することの意味、支援を受ける側の想いなどを聞いた。
(聞き手:AAR Japan 太田 阿利佐/11月18日にインタビュー)
忘れないでくれてありがとう
――2022年9月にポーランド、オーストリア、スロバキアを旅して、避難中のウクライナ難民の方々を訪ねたそうですね。
サヘルさん 私は仕事で海外に行った時、その国の孤児院や児童養護施設を訪問して、何かしら必要なものを届けることにしているんです。今回はポーランドで舞台公演があり、この機会に周辺の国々に避難したウクライナの方を支援したいと思って、事前に自分でいろいろ調べて、連絡を取って、一人で回りました。ポーランドのウクライナ国境近くでお会いした難民の方の方をはじめ、スロバキアで出会った方々に「私たちがここに存在していることを忘れないでいてくれて、ありがとう」と言われた時、はっとしました。メディアが注目するところでさえ、時間が経つと関心が薄れてしまう。そうでないところには支援も届かず、すごく大変で、すごく孤独なんだと実感しました。
私が今、支援しているのは、イランからイラクへ逃れたクルドのご一家や宗教少数派ヤジディー教の人々、そしてシリアからヨルダンに逃れた人々。私は出会ったご家族や子どもたちとできるだけ連絡を取り続けているんです。生活費や医療費の支援とはまた別に、何かあった時に会話できる、思い浮かべる顔があるという寄り添い方をすることが、実はすごく大事な心のケアの一つだと思っています。
「魚の釣り方を教える」人に
――難民支援や児童養護に関わる活動を始めたきっかけは何ですか。
サヘルさん 2010年にNHKの「地球ドキュメント ミッション」という番組のキャスターを務め、人権活動家である土井香苗さんと出会ったり、世界のさまざまな問題や出来事を学んだりしました。貧困や戦争などの苦しい状況の中で生まれてくる子どもが実にたくさんいると知り、その話を母にすると「あなただって、この子たちと同じ状況にずっといたかもしれない。あなたは縁があって私と出会って、ここまで来たけど、あなたは自分の原点を忘れてはいけない。その原点を、あなたがこの子たちのロールモデルになる力にしてほしい」と言われたんです。イラン・イラク戦争(1980~88年)で家族を失い、孤児だった私は確かに彼らと同じでした。ありがたいことに、私はいろんな人に助けられて29年間も日本で暮らしてきました。日本では、蛇口をひねれば安全な水が出るし、教育だって普通に受けられる。これって決して当たり前ではない。奇跡です。でも、私はそれに慣れ切ってしまっていた。まずは自分で世界を見ようと思い、母のアドバイスもあってインドに行きました。インドは母が一時期、暮らしていた国です。
靴もはかずに物乞いをする子がたくさんいて……かわいそうで、たくさんおカネを渡しました。帰国して母にすごく怒られました。「おカネは悪い大人に吸い上げられる。あなたはあの子たちが不幸になる手助けをしただけだ」と。そして、いわゆる「魚をあげる人」ではなく、「魚の釣り方を教えてあげる人になりなさい」と教えられました。
もちろん今、食べ物が必要な人もいるでしょう。だから私は、一定期間は魚でいいけれど、その後は釣りの方法を伝えて、支援がいらなくなるやり方がいいと考えています。教育は何より大事です。数年前からインドネシア・ティモール島のアナという女の子の学費を支援しています。ヨルダンのシリア難民キャンプで学校を運営しているNGO、バングラディシュでストリートチルドレンのための学校をつくったNGOも支援しています。

カンボジアの孤児院を訪問し、子どもたちと交流するサヘルさん=(本人提供)
子どもの笑顔の裏には
――サヘルさんは、よく現地に足を運んでいます。現地で見えてくるものはありますか。
サヘルさん カメラを向けると子どもたちは笑ってくれます。無邪気に笑っているように見えて、実は子どもたちって、笑うことしかできない。親が苦しんでいるのを敏感に察しているからです。特に難民キャンプや施設の子どもは、外部の人がきたら笑う。親や家族の前でも、自分たちが明るく振舞わないと耐えられないということもあって笑う。笑顔の裏には、いろんな思いがあることを再発見しました。再発見というのは、私自身もそうだったからです。孤児院にいる時は、誰かが自分を引き取って、救ってくれるようにと笑っていました。日本の学校でいじめにあって自殺を考えていたような時にも、母に心配をかけたくなくて、笑っていました。
ヨルダン北部のザアタリ難民キャンプで出会ったリムという女の子が、今でも携帯電話で連絡をくれるんです。でも、言葉が通じないから何度も何度も「アイ・ラブ・ユー」って繰り返すだけ。私も「アイ・ラブ・ユー」って何度も返す。30分ぐらい。でも、それだけでいい。誰かとつながっていることが必要なんです。私は関わり続けることが必要だと思っています。
皆さんが「サヘルはいろんな活動をしていて、すごいね」「すてきだね」と言って下さいますが、でも当事者の方にお会いすると、自分は何もできていないということを自覚させられて、辛くて、悲しくて、苦しい。9月にウクライナ難民の方々に会って、支援を届けた後も、毎晩ホテルで泣いていました。それに私はウクライナ難民の方々がこれから味わう怖さも知っています。彼らへの関心も支援も、数年で薄れていくでしょう。今は生き延びるために必死ですが、家や生活が落ち着いて「安心できる」状態になった時、蓋をしていた感情や、目にしたひどい光景の数々が蘇ってくる。何一つ解決されていないんです。一番の問題はこれから数年後だと思っています。

表情豊かに語るサヘルさん
支援に大小はない
――でも支援を続けていくのは大変なことです。大切なことは何でしょうか。
サヘルさん 支援やサポートは難しくて、終わりがない。私自身は、関わり続けることが非常に大切なことだと思っていますが、その中では当然、やれないことも出てくる。自分にできること、できないことを、はっきり相手に伝えることが必要だと思っています。それと、まずは自分や家族の生活が大丈夫な状態にして、そのうえで自分がやりたいと思った時にできる範囲で始めるのがいい。頑張ったところで、無理なものは持続できなくなってしまいますから。支援に大小はありません。500円だってすごく立派な支援です。その思いは、受け取る人にとってはすごく温かく、助けられるものです。私は食事もできない貧しい生活をしていた時に、スーパーで働く女性から食べ物をいただいたり、親子で公園で暮らしていた時に小学校の給食のおばさんが声をかけてくれ、自宅に泊めていただいたり……そうして支えられました。だからどんな小さなことでも、できることから始めてほしいと思います。そして、支援はしても、支配はしないでほしい。

バングラデシュとインドの国境近くにある男の子のための教育施設を訪問したサヘルさん(中央)=(本人提供)
まずは会って知り合うことから
――親切な人たちがいる一方で、難民や外国人にひどく冷たい人たちもいます。
サヘルさん 今は、だれしもが難民になってしまう可能性がある世の中だと思います。自分の家族や祖国を離れ、命からがら逃げてくる難民に、なりたくてなる人はいません。そういう人たちのことをよく知らない、当事者の目も見ていない人が「嫌だったら出ていけ」なんて冷酷なことを、どうして言えるのかと思います。
私もよく同じことを言われるんです。私は日本を愛しているし、仕事をして、一生懸命税金も払っています。日本では人手が不足していて、すでに多くの建築物も衣類も食べ物も外国人労働者の手を借りて供給されています。日本は人手がほしい。彼らは働きたい。本来お互い助け合えるのに、なぜ背を向けるのか……。もう少し、隣人だよ、助け合えるんだよ、寄りかかれるんだよ、友達になれるんだよ、と分かってほしい。
難民や外国人労働者のことを知らないし、知ろうともしない人がいるのだと思います。当事者と知り合えば全然違ってくる。11月23日に埼玉県川口市で「難民・移民フェス」というイベントがあって、私を応援してくださっている仲間たちと一緒に参加しました。クルド難民やウクライナ難民、ミャンマーから来た方々がお店を出していて、私たちはクッキーとか綿あめとか、アフガニスタン難民のお母さんであるビビグルさんと一緒に作ったドーナツとかを販売して、皆さんと交流しました。
私と母は、ボランティアで難民の方の電話通訳(ペルシャ語、ダリ語)もしているんですが、日本では難民の方がものすごく孤独です。日本の難民受け入れは、問題が山積している。一方で「何かやりたい」と思っている日本の人たちもたくさんいます。だから「もうアクションするしかない」と思って、「さへる畑」というファンクラブというか、仲間が集える場をつくって、フェスに参加しました。この移民・難民フェスのように、やれることを一生懸命やっていくのはとても大事だと思っています。

埼玉県川口市で開催された「難民・移民フェス」に、「さへる畑の」仲間と一緒に参加し、お菓子などを販売するサヘルさん(右)
――今年1月に出されたご著書『言葉の花束 困難を乗り切るための“自分育て”』(講談社)には、サヘルさんの体験から生まれてきた言葉がつづられています。
サヘルさん この本で一番読んでほしいのは、母の言葉の数々です。まだ大学生だった母は、家族の反対を押し切って私を養女にしてくれました。血がつながっていることがすべてじゃない。どんな人も誰かの家族になれるし、誰かとともに生きることはできる。それが伝えられたらうれしいです。

人に助けられたからこそ
――サヘルさんにとって「支援する」ことの意味は?
サヘルさん 私、教育の現場をAARさんが守ってくださっているのが、とてもうれしいんです。人間は読み書きができて、知識を蓄えて、いろんな本を読むことができれば、自分の考えを育むことができる。でも、それがないと「これしかない」と教え込まれたことに洗脳され、それが民族紛争やテロにつながっていく。そうしないためにも、子どもが学ぶ環境を整えるのがとても大事だと思っています。
今、私が支援している学校に通う難民やストリートチルドレンの子どもたちが、全部で400人くらいいます。その中のたった一人でもいい。起業家とか、その国を良い方向に引っ張っていくリーダーになってくれれば、他の子どもたちのロールモデルになるじゃないですか。そして、私もそうですが、人に助けられたからこそ、次の人を助けたいと思ってくれると思う。そうすれば世界は良くなっていくと信じています。
ひとこと 「難民・移民フェス」の日は大雨で、とても寒かったです。その中で、薄いカッパ一枚で髪を雨で濡らし、笑いながらクッキーを売るサヘルさんは、とても楽しそうで、美しかった。「美しい」という言葉は、姿形だけではなく、生き方や生き様に使う言葉なんだと、改めて気が付きました。アフガニスタンのお母さんのドーナツはとても素朴な味。かみ応えがあって、食べると気持ちが温かくなりました。(O)
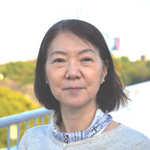
太田 阿利佐Ota Arisa東京事務局
毎日新聞記者を経て、2022年6月からAAR東京事務局で広報業務を担当。



